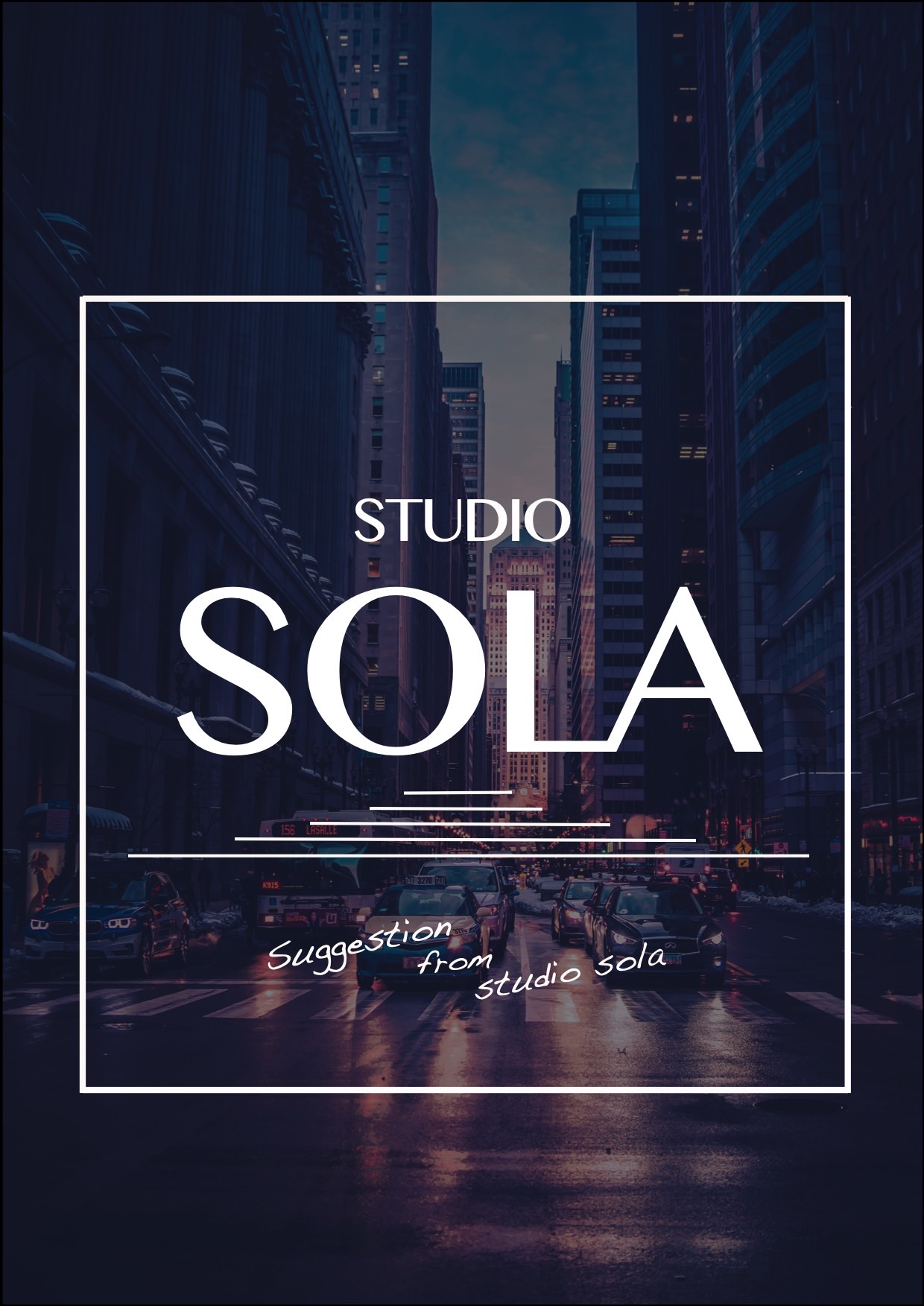スネアのチューニングについての知識
Studio Solaのスネアのヘッドを張り過ぎと感じてしまう方は、
一度以下を考えてみて下さい。
国内では、スネアの音色を低くしたい時に『ヘッドのチューニングを下げて低くする』という事が広まってしまっていますが、果たしてこれは正しい知識なのでしょうか?
答えは、間違いです。勿論、特定の狙いがある場合は、そういうやり方もあります。
間違いである根拠
多くの楽曲のドラム演奏は、一打ごとのスネアの音色の差異を抑える必要があります。
緩いチューニングで同じ音色を出し続けるには、相当な鍛錬が必要です。
逆に高いチューニングでは、誰でも安定した音色を出す事が出来ます。
さらに、緩いチューニングにおいては、スネアの口径、銅の深さ、銅の材質、ヘッドの材質、スナッピーの材質、これらの違いが出ません。
素材やサイズに拘る人が多いにも関わらず、胴鳴りしていない人が多いという可笑しな事になっています。
では、低い音を聴かせたい時は、どうするのが正解なのでしょう?
そもそも、アンサンブルの中で鳴らされるスネアの音の高低は、ヘッドのチューニングの高さではありません。容積や材質によるものです。これを知らない日本人が多過ぎます。
何も難しくありません。和太鼓が、あれだけ高いテンションで皮を張ってあるのに、凄く低い音が出ているのを思い浮かべて下さい。
さらに音色を低くするには、ミュートやエフェクトシート、無ければタオルなどを使います。レコーディングでは常套手段です。なぜなら、鳴らし切った音量の素材の音程だけを下げる必要があるからです。スネア自体の音量が下がっていては意味がありません。
この知識が欠けているせいで現在、国内のメジャーアーティストの多くは音量が小さ過ぎます。これも日本のポピュラーシーンが〝鎖国状態〟である顕著な例です。またこれは〝トリガー有りきのパックレコーディング文化〟で生まれた勘違いでもあります。
|
この理論の礎は、アメリカの偉大なミュージシャン、故ジョー・ポーカロ氏の教えです。 彼のお弟子さんから直接教わったものです。奏法だけでなく楽曲、楽器、音響の観点からも正しい多角的な正しい知識の良い例です。 欧米をはじめ世界中のレコーディングでは、何十年も前から常識です。プレイヤーなら一度は通る バンド〝TOTO〟(ポーカロ氏の息子さんたちのバンド)の作品を聴けば納得して頂けます。
|
Studio Sola